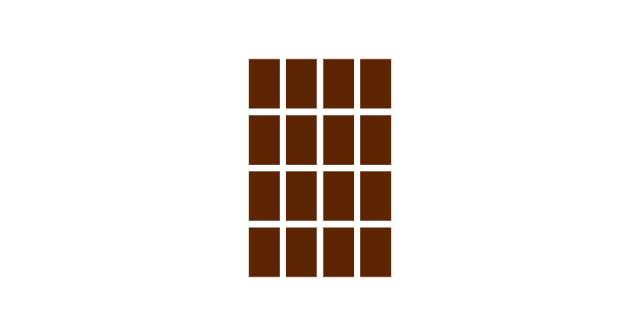【加筆内容】ダークチョコレートは酸化ストレス・体内炎症に効くのか?
これまで見てきたようにダークチョコレートはカカオの量が多く、そのため、ポリフェノール(カカオポリフェノール・フラバノール)も多く含まれております。そして2000年のINRA(INRAE)の研究なんかを見てみると、ダークチョコレートのポリフェノール量は、赤ワインやコーヒー、リンゴなどの食品よりも多いそうなんですな。
また1998年の株式会社明治の研究によれば、他のポリフェノール同様、カカオポリフェノールにも抗酸化作用があるそうで、更に2000年の株式会社明治の研究では、カカオポリフェノールには、カテキンやエピカテキン(緑茶に多く含まれる成分)、プロシアニジン(ブドウやナッツなんかに多く含まれる成分)が含まれるみたい。
そんなダークチョコレートだからこれまで見てきたように、脳機能がアップしたんでしょうね。事実、2004年のブリストル大学の研究や2013年のナバラ大学の研究では、チョコレート(カカオ)に含まれるメチルキサンチンにより、中枢神経系を刺激すると出てますし…。
では、これだけポリフェノール・抗酸化作用のポテンシャルを秘めているダークチョコレートなら、酸化ストレスや体内炎症にも良いんじゃないか…?ってことで、今回チェックした研究を見てみましょう…!
ダークチョコレート・ココアと酸化ストレス・体内炎症(慢性炎症)の関係について系統的レビューとメタ分析を行ってみた…!
そもそも体内炎症(慢性炎症)は様々な慢性疾患の発症、進行の促進、悪化と関係があると先行研究で出ております。
そして酸化ストレスは、フリーラジカル(≒多いと酸化ダメージ・老化を引き起こす)の生成が体内の抗酸化力を上回った場合のことを言いまして2002年のヴァンダービルト大学の研究によれば、タンパク質や脂質、核酸(≒DNA)にダメージを与える際に発生するんですな。
そして酸化ストレスは、フリーラジカル(≒多いと酸化ダメージ・老化を引き起こす)の生成が体内の抗酸化力を上回った場合のことを言いまして2002年のヴァンダービルト大学の研究によれば、タンパク質や脂質、核酸(≒DNA)にダメージを与える際に発生するんですな。
そんな酸化ストレスと体内炎症ですが、食事から抗酸化物質を摂取することで防げることが先行研究で分かっております。そしてダークチョコレート・ココアには、フラボノイドなどのポリフェノールが豊富に含まれており、ポリフェノールには抗炎症作用・抗酸化作用があります。
つまりダークチョコレート・ココアで酸化ストレスと体内炎症の対策が出来るかもしれないんですな。んがしかし、そこん所を調べた先行研究はあるものの、実際よく分かっていなかったみたい。そこで今回、系統的レビューとメタ分析を用いてチェックしてみることにしたんだとか。
まず研究者たちは、2024年4月までに発表されている該当研究をPubMed、Web of Science、SCOPUSで検索してみたそうな。また参考文献リストや手作業でも探してみたらしい。すると全部で1,194件の研究が見つかったそうな。
次にこの中で被っている物、質の低い物を除いていったそうで、最終的に選ばれた研究は33件とのことでした。
この33件の特徴はこんな感じ。
- サンプル範囲:15±63人~122±68人
- 実験期間:2週間~12週間
- 実験デザイン:13件はクロスオーバーデザインだった。
それと用いたカカオ(ココア)の摂取方法も見ておきましょう。
- カカオ(ココア)パウダー
- カカオ(ココア)入り飲料
- チョコレートバー
まぁ、一般的な方法ってことですね。
それと今回調べた酸化ストレスと炎症マーカーも見ておきます。
- CRP(C反応性タンパク)
- IL-6(インターロイキン6)
- TNF-α(腫瘍壊死因子)
- MDA(マロンジアルデヒド:脂質過酸化物の分解物・脂質過酸化マーカー)
- 一酸化窒素(NO)
- P-セレクチン(細胞活性化マーカー)
- E-セレクチン(細胞活性化マーカー)
- TBARS(チオバルビツール酸反応性物質:脂質過酸化マーカー)
それではメタ分析の結果を見てみましょうか。
【CRP(C反応性タンパク)】
【CRP(C反応性タンパク)】
- 18件の研究から、1,379人の参加者(介入群689人、コントロール群690人)がCRP(C反応性タンパク)レベルを測定した。
- ダークチョコレート・ココアによるCRPの減少は有意ではなかった(WMD-0.08mg/l)
- 但しCRPの測定の種類、フラボノイド(ポリフェノール)の摂取量、研究場所の違いが原因である可能性があった。
- フラボノイド(ポリフェノール)の摂取量が1日450mgより多いとCRPの減少で大きな効果が見られた…!
- フラボノイド(ポリフェノール)の摂取期間が4週間以下だとCRPの減少で大きな効果が見られた…!
- 健康な参加者だとCRPの減少で大きな効果が見られた…!
- 標準的なCRPの測定だとCRPの減少で大きな効果が見られた…!
- ヨーロッパで実施された研究だとCRPの減少で大きな効果が見られた…!
- メタ分析によれば、CRPレベルはフラボノイド(ポリフェノール)の摂取量や介入期間によって有意な影響を受けないみたいだった。
【IL-6(インターロイキン6)】
- 10件の研究から、590人の参加者(介入群309人、コントロール群281人)がIL-6(インターロイキン6)レベルを測定した。
- ダークチョコレート・ココアによるIL-6の減少は有意ではなかった(WMD0.10pg/ml)
- 但し摂取量、摂取期間、研究場所、参加者のBMIと健康状態の違いが原因である可能性があった。
- ヨーロッパで実施された研究では、摂取期間が4週間以下で、BMIが25以上(=過体重・肥満)の非健康者を対象にしたが、IL-6が有意に減少していた…!
- メタ分析によれば、IL-6レベルはフラボノイド(ポリフェノール)の摂取量に関係しており、介入期間は関係なかった…!
【TNF-α(腫瘍壊死因子)】
- 7件の研究から、427人の参加者(介入群228人、コントロール群199人)がTNF-α(腫瘍壊死因子)レベルを測定した。
- ダークチョコレート・ココアによるTNF-αの減少は有意ではなかった(WMD-0.37 pg/ml)
- 但し参加者のBMIと健康状態、研究場所の違いが原因である可能性があった。
- ヨーロッパで実施された研究では、BMIに問題ないが非健康者を対象にしたところ、4週間より多い期間にTNF-αが有意に減少していた…!
- メタ分析によれば、TNF-αレベルは有意な影響を受けないみたいだった。
【MDA(マロンジアルデヒド)】
- 9件の研究から、626人の参加者(介入群330人、コントロール群296人)がMDA(マロンジアルデヒド)レベルを測定した。
- ダークチョコレート・ココアによるMDAの減少は有意だった(SMD-0.69)
- 但し摂取期間、研究場所、参加者のBMIの違いが原因である可能性があった。
- フラボノイド(ポリフェノール)の摂取量が1日450mg以下だとMDAの減少で大きな効果が見られた…!
- フラボノイド(ポリフェノール)の摂取期間が4週間以上だとMDAの減少で大きな効果が見られた…!
- 北アメリカ南アメリカで実施された研究だとMDAの減少で大きな効果が見られた…!
- 過体重・肥満の参加者だとMDAの減少で大きな効果が見られた…!
- メタ分析によれば、摂取量・摂取期間とMDAレベルは有意な影響を受けないみたいだった。但し、摂取期間とMDAレベルは有意だった…!
【一酸化窒素(NO)】
- 5件の研究から、194人の参加者(介入群94人、コントロール群100人)が一酸化窒素(NO)レベルを測定した。
- ダークチョコレート・ココアによる一酸化窒素の増加は有意だった(SMD2.43)
- 但し各研究の違いが原因である可能性があった。
【P-セレクチン】
- 3件の研究から、626人の参加者(介入群330人、コントロール群296人)がP-セレクチンレベルを測定した。
- ダークチョコレート・ココアによるP-セレクチンの減少は有意ではなかった(WMD-2.7ng/ml)
【E-セレクチン】
- 4件の研究から、212人の参加者(介入群106人、コントロール群106人)がE-セレクチンレベルを測定した。
- ダークチョコレート・ココアによるE-セレクチンの減少は有意ではなかった(WMD-1.85ng/ml)
- 但し各研究の違いが原因である可能性があった。
【TBARS(チオバルビツール酸反応性物質)】
- 3件の研究から、288人の参加者(介入群143人、コントロール群145人)がTBARS(チオバルビツール酸反応性物質)レベルを測定した。
- ダークチョコレート・ココアによるTBARSの減少は有意ではなかった(WMD-0.22µmol/L)
ちょっとポイントをまとめてみましょうか。
- ダークチョコレート・ココアはMDA(マロンジアルデヒド)を有意に低下させた…!
- つまりダークチョコレート・ココアには、脂質(コレステロール)の酸化を抑える働きがありそうだった…!
- ダークチョコレート・ココアは一酸化窒素(NO)を有意に上昇させた…!
- つまりダークチョコレート・ココアには、血管拡張機能がありそうだった…!
- ダークチョコレート・ココアの抗炎症効果は、1日450mgより多く取った場合、4週間以下という短期間で取った場合に見られた…!
因みにCRPとMDAの結果のみがエビデンスレベルが高かったらしく、後は中程度以下だったみたいです。
個人的考察
ということで、どうやらダークチョコレート・ココアには、酸化ストレス・体内炎症(慢性炎症)を改善する可能性がある様子でした。