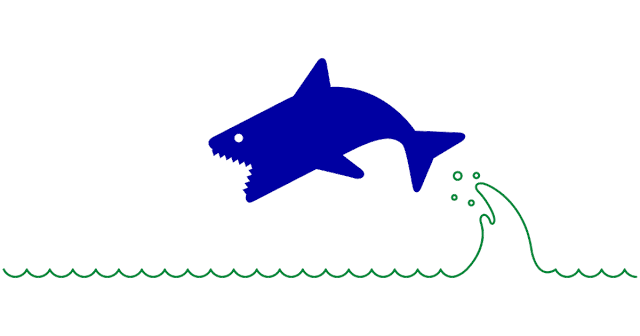【まとめ】オメガ3脂肪酸が足りないと何がヤバいのか?多いと何が良いのか?
人間の体は健康体に戻るようにできているため、太ることは有り得ない。しかし、セットポイントが狂ってしまうと太ってしまう…。これは以前に書いた通り。また、セットポイントが上がってしまう理由の中にオメガ3脂肪酸が不足しているのも原因の一つだよ~というのを書いていました。ここを掘り下げるためにチュートリアルとして、脂肪酸について前回軽くまとめた次第であります(因みにオメガ6脂肪酸についてはこちらをご覧ください)
オメガ3脂肪酸ってなに…?
オメガ3脂肪酸ってのは、多価不飽和脂肪酸(PUFA)の一つに属しておりまして、1991年の研究なんかを見てみると、
- エイコサペンタエン酸(EPA)
- ドコサヘキサエン酸(DHA)
- α-リノレン酸(ALA)
といった種類がございます。
そしてフィッシュオイルは、エイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)が唯一濃縮されて含まれている食べ物で主な供給源ともなっております。一方、植物に含まれる主要なオメガ3脂肪酸がα-リノレン酸(ALA)となっております。
んで2012年のバレアレス諸島大学の研究によれば、α-リノレン酸(ALA)は、体内で合成できず、食品やサプリなどから摂取する必要があるそうです。そのため必須脂肪酸となっております。対して、エイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)は、体内でα-リノレン酸(ALA)から生成することが可能なんだとか。そのため食事からの摂取は必須と考えられていないみたい。
そんなエイコサペンタエン酸(EPA)・ドコサヘキサエン酸(DHA)、α-リノレン酸(ALA)は以下の物に含まれているそうな。
そんなエイコサペンタエン酸(EPA)・ドコサヘキサエン酸(DHA)、α-リノレン酸(ALA)は以下の物に含まれているそうな。
- エイコサペンタエン酸(EPA)・ドコサヘキサエン酸(DHA):2008年のモンクトン大学の研究によると、EPAとDHAは、ビンナガマグロ、サーモン、サバ、イワシ、ニシンなどの脂肪の多い魚から摂取できる。つまりイメージは青魚。余談だが卵なんかにも含まれていたりする。
- α-リノレン酸(ALA):2003年のアメリカ心臓協会(AHA)の勧告によると、ALAは、クルミ、亜麻仁、キャノーラなどのナッツ・植物油から摂取できる。
まぁ、メインはやっぱ魚でしょうね。ナッツや植物油はオメガ6脂肪酸も同時に結構とることになるので。
オメガ3脂肪酸は様々な健康効果がある…!
そんなオメガ3脂肪酸は、様々な健康効果がありまして、例えば- 2004年の西オーストラリア大学の研究:体内のオメガ3脂肪酸が足りないと全身に炎症が起きる…!
- 1994年のオールボー大学の研究:オメガ3脂肪酸は心血管疾患の予防と改善に効果がありそう…!
- 2014年の書籍:オメガ3脂肪酸でストレスが減る…!
- 2011年の研究:オメガ3脂肪酸で脳機能がアップする…!
- 2015年のサウサンプトン大学の研究:オメガ3脂肪酸は抗炎症作用がすごい…!
- 2013年のサウサンプトン大学の研究:オメガ3脂肪酸は免疫調節機能がある…!
- 2006年のタフツ大学の研究:オメガ3脂肪酸で認知症発症リスクが47%も有意に減少した…!
- 2010年のカリフォルニア大学アーバイン校の研究:体内のオメガ3脂肪酸が少ないとアルツハイマー病リスクが高かった…!
って感じ。
んで、オメガ3脂肪酸は牛肉や豚肉、鶏肉やラム肉などにも入っているんですが、飼育環境(抗生物質の使用とか)で、かなりオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸との比率に差があるんですよね。そのため、安定して摂取するならやはり魚を中心とした摂取方法がベストとなります。
オメガ3脂肪酸・フィッシュオイルの効果はものすごい…!
2002年のCenter For Genetics Nutrition and Healthの研究によると、オメガ3脂肪酸のメリットについてレビューしてみたそうです。
そもそも脂肪酸(多価不飽和脂肪酸)の中で最強の免疫調節・活性化機能を持つオメガ3脂肪酸はフィッシュオイルに含まれる成分。
主な種類としては、
- エイコサペンタエン酸(EPA)
- ドコサヘキサエン酸(DHA)
- α-リノレン酸(ALA)
などがあります。
その効果・メリットは非常に多いそうでレビューによるとこんな感じ。
- 脳細胞の伝達スピードがアップする…!
- 遺伝子発現が活性化する…!
- 高い抗炎症作用・抗酸化作用を持っている…!
- 炎症性疾患と自己免疫疾患の予防や症状改善に役立つ…!
すばらしい効果ですねー。
またオメガ3脂肪酸により効果が見込めそうな炎症性疾患と自己免疫疾患はこんな感じ。
- 冠状動脈性心疾患(CHD)
- 大うつ病
- 老化
- ガン
- 関節炎
- 全身性エリテマトーデス
- 関節リウマチ
- クローン病
- 潰瘍性大腸炎
- 乾癬
- 多発性硬化症
- 片頭痛
オメガ3脂肪酸の抗炎症作用が、炎症性サイトカインやIL-1(インターロイキン1)に作用し、慢性炎症対策になるみたいですね。結果、腸内環境が改善し、上記に挙げたような様々な症状の予防、改善になるみたい。
特に青魚にはビタミンB群(ビタミンB6・ビタミンB12)、ビタミンDといった成分も多いんでぜひ積極的に食べていきたいですねー。
サプリメントはダメなのか…?
魚が嫌いな人や魚の調理が面倒だな…って方もいるのではないでしょうか…?そんな時に検討材料として挙がるのがサプリメントでしょう。
でも、ちょっと待ってください…!代替品としてサプリを選んでも期待した効果が得られない可能性があるんですよ。
ということで魚のサプリ(フィッシュオイルサプリメント)ついてみていきます。
市販のフィッシュオイルサプリ32品目を調べてみた…!
2015年のオークランド大学の研究によると、ニュージーランドで販売されているフィッシュオイルサプリメントの品質と含有量を調べてみたそうです。フィッシュオイルサプリメントは全部で32種類あったそうで、これらの商品の品質をチェックしたとのこと。んで、結果が、
- 32種類のうち、3種類しかラベルに表記されたエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)の含有量以上の量を含んでいなかった…!
- フィッシュオイルサプリメントのほとんどが酸化マーカーの推奨レベルを超えていた…!
とのこと。
つまり、オメガ3脂肪酸のサプリメントはラベルに表記された含有量をほとんど含んでいないみたいですし、フィッシュオイルの酸化もかなり進んでいたみたい…。これは意味ないな…。
因みにフィッシュオイルは非常に酸化しやすいらしく、これを防ぐのは相当難しいみたいです。う~ん。サプリメントで代用…!とは気軽に行けなそうですね~。
やっぱオメガ3脂肪酸を摂取するならフィッシュオイルサプリメントよりも普通に魚を食べた方が良いみたい…!
2003年のウェールズ大学のRCTによると、70歳未満の狭心症を患う男性3,114人を対象に以下の4つのグループにランダムに分かれてもらったそうです。
- 毎週魚(サーモン)を食べるか、フィッシュオイルサプリメントを飲むようアドバイスした
- 果物や野菜、オーツ麦を積極的に食べるようアドバイスした
- 上記1と2の両方を伝えて食べてもらうようアドバイスした
- アドバイスしない(対照群)
その後3〜9年後の死亡率を確認したとのこと。
結果、
- 果物などを積極的に食べるようアドバイスされたグループよりも魚などを積極的に食べるようアドバイスされたグループの方がアドバイスをきちんと守る人が多かった…!
- 魚などを積極的に食べるようアドバイスされたグループは、そうでないグループよりも心疾患のリスクが低かった…!
- 魚を積極的に食べていた人と、フィッシュオイルサプリメントを摂取していた人を比べたら、魚を積極的に食べていた人の方が心疾患のリスクが低かった…!
そうです。
これをみると効果を一番受けつつ続けていけるのは普通の魚を積極的に食べるって方法みたいですね。
ということで、サプリは使わず魚は普通に食べた方が良いよって話でした。
やっぱサバ缶の水煮は最強ってことで(笑)
フィッシュオイルサプリメントのまとめ
まとめとして、オメガ3脂肪酸は非常に酸化しやすいという特徴があります。また、サプリメントを作るのは製造工程上、非常に難しいらしく、またコストもかなりかかるそうな。そして上記の通りサプリでは効果がなくなってしまう、又は逆に悪影響すらあるみたいです。巷に売っているオメガ3脂肪酸のサプリメントには注意が必要ってことですね。
これをみてもどのサプリメントが良いのかいちいち調べるよりも魚を食べた方が良いのは言うまでもありません。
魚をフライにして食べない方が良い…!
そして食べ方にも注意が必要です。気を付けるべきは魚をフライにして食べないこと。
例えば2003年のワシントン大学の研究によると、
- 魚の摂取量が多いほど心不全のリスクは低くなる…!
- 但し、揚げた魚(フライ)の摂取量が多いほど心不全のリスクは高くなる…!
とのこと。
つまり魚を揚げちゃうとせっかくのメリットが失われちゃうんですな。
そのため、魚の調理法として揚げるのは不適切だそう。やっぱり魚は刺身、焼き魚、煮つけ、缶詰が良さそうですね。
また2013年のフレッドハッチンソンがん研究センターの研究では、男性3,041人に普段どれぐらい揚げ物を食べるかアンケートを実施し、病歴との関連性を調べてみたそうです。
アンケートにあった揚げ物は、
- フライドポテト
- フライドチキン
- フライドフィッシュ
- ドーナツ
- スナックチップ(ポテトチップみたいなもの)
とのこと。
結果、週1回未満しか食べない人と比較して、週1回以上で揚げ物を食べる人は、前立腺がんになる可能性が高かった…!そうです(スナックチップだけは関連がみつからなかったそうですが、何故かは不明)
結果、週1回未満しか食べない人と比較して、週1回以上で揚げ物を食べる人は、前立腺がんになる可能性が高かった…!そうです(スナックチップだけは関連がみつからなかったそうですが、何故かは不明)
因みに原因は高温で揚げることによる酸化です。またサラダ油などのオメガ6脂肪酸を使ってしまうのも原因の一つとなっております。
魚の摂取が脳にどのような影響をもたらしているのか9年間の食事から調べてみた…!
サプリとフライはやめた方が良いってのは、こちらの研究でも分かっておりまして、2014年のピッツバーグ大学などの研究によると、認知症になっていない65歳以上の高齢者260人を対象に魚の摂取が、脳にどのような影響をもたらしているのかを調べたんだそうな。因みに9年間の食事内容を調べつつ、合わせてMRIで脳内を見たそうです。結果、最低週1回、焼き魚を食べるだけで、
- 脳の記憶エリアが4.3%も厚みが増していた…!
- 認知を司るエリアが14%も厚みが増していた…!
とのこと。
高齢者を対象にした実験ですが、これはなかなかうれしいですね~。特に認知症になっていない方を対象としていますので、認知症の予防になるのは助かりますな~。
しかも週1ならハードルも低くかなり楽に導入可能ですね…!
でも、注意点が見つかっておりまして、
- 魚をフライにして食べた場合、脳の厚みに変化はなかった…!
ということです。つまり、フライにしてしまうとメリットが全て消えてしまうということですね。う~ん。ショック…。
それとオメガ3脂肪酸が良いならサプリだ…!って方もいるかもしれませんが、それもどうやらダメそうなんですよ。というのも脳機能をアップさせるにはオメガ3脂肪酸の他にもタンパク質やセレン、鉄、ヨウ素、亜鉛なんかも同時に摂取する必要があるみたいで、これらをサプリで摂ろうとするくらいなら魚を食べた方が早そうなんですよね。
ということで、やっぱサプリではなく魚を食べた方が手っ取り早くて良さそうですね。それとせっかく食べるならフライ以外の食べ方をしていきましょう…!
DHAには脳を含む全身の炎症を抑える効果がある…!
1999年の研究や2007年のブリティッシュコロンビア大学の研究によるとDHAは脳を含む全身の炎症を抑える効果があったんだそうな。つまり、青魚などを食べると炎症が抑えられると…。特に脳の炎症はうつ病の発症や悪化の原因の一つと考えられておりますんで、メンタル安定のためにもぜひ、意識していきたいところですね~。
オメガ3脂肪酸は筋肉の維持、生成に役立つ…!
2011年のワシントン大学の研究によると食事でオメガ3脂肪酸の摂取量を増やすと、加齢などによる筋肉量の減少を抑える効果がありそうってのは分かっていたけど、健康的な人を対象に調べたことがなかなかなかったんで調べてみようと思ったそうです。この研究では25歳から45歳の健康な9人を対象に8週間、オメガ3脂肪酸を摂取してもらったんだとか。具体的には、1日4gのフィッシュオイルを飲んでもらい、筋肉のタンパク質合成のスピードがどのように変わるか(どれぐらい筋肉が作られるか)を見たとのこと。
結果、1日4gのオメガ3脂肪酸(フィッシュオイル)の摂取で筋肉のタンパク質合成スピードが大幅にアップしたそうです。更に、筋トレ後のアナボリックスピード(筋肉生成スピード)もアップしていたそうで、これはなかなか期待できそうな感じ。
サンプル数が9人と少ないのはちょっと残念ですが、魚を食べるだけで、運動をしなくても筋肉量が保てるのは結構嬉しい話ですよね。
毎日のオメガ3脂肪酸+有酸素運動で脂肪燃焼効果がアップする…!
2004年のアルベルト・アインシュタイン医学校の研究によると、普段から運動をしている21〜27歳の男性7人を対象に、オメガ3脂肪酸と有酸素運動を組み合わせて脂肪燃焼効果が上がるのか調べてみたそうです。実験は最大酸素摂取量の60%の力で60分間、ジョギングをしてもらいつつ、以下の3つの方法をランダムな順序で行ってもらったそうな。- 食事をしない
- 4時間後に高脂肪食を摂る
- 4時間後にオメガ3脂肪酸を摂る
因みにオメガ3脂肪酸は60%のエイコサペンタエン酸と40%のドコサヘキサエン酸が含まれたサプリメントで摂取したとのこと。次に参加者は1日4gのオメガ3脂肪酸を3週間飲み続けながら、同様の試験を3回ランダムな順序で繰り返したそうです。
結果、
- 普段あまりオメガ3脂肪酸を摂取していない人が急に摂取しても有酸素運動による脂肪燃焼効果に影響はなかった…。
- しかし、毎日オメガ3脂肪酸を摂取している人は有酸素運動による脂肪燃焼効果が約10%程アップしていた…!
とのこと。
毎日オメガ3脂肪酸を食べながら有酸素運動をすると痩せやすくなるみたいですねー。
オメガ3脂肪酸の摂取量を増やすと体脂肪が減った…!
1997年のフランソワ・ラブレー大学の研究によると、オメガ3脂肪酸のダイエット効果について調べてみたそうです。実験は6人のボランティア(男性5人、平均年齢23歳、BMI=21.9)を対象にしたそうで、最初の3週間は普通の食事(炭水化物52%、タンパク質16%、脂肪32%)を自由に食べてもらったそうです。次に10〜12週間後に同じ食事をしてもらったらしい。その時、脂肪6gをオメガ3脂肪酸6gに置き換えて3週間更に様子を見たそうな。
結果、
- カロリー摂取量に違いは出なかった…。
- しかし、体脂肪(DXAで調べた)はオメガ3脂肪酸の摂取量を増やすと減少した…!
とのこと。
サンプル数が少ないのが心もとないですが、平均体型の方がオメガ3脂肪酸の摂取量を増やしただけで、体脂肪が減ったってのは嬉しい結果ですね。
オメガ3脂肪酸で細胞膜の機能をアップさせ、炎症を抑えるのが理由みたい
なぜ脂肪燃焼効果がアップするのかですが1998年のシンシナティ大学の研究によると、オメガ3脂肪酸は細胞膜に急速に組み込まれるらしく、神経伝達スピードの活性化や遺伝子発現(タンパク質が作られる)、細胞分化(細胞が特定の機能を持つ細胞に変化すること)に影響を及ぼし、また、炎症性サイトカイン産生、炎症反応を抑える働きがあるからみたい。
つまり、炎症を抑えつつ、効率良く栄養素やホルモンを取り入れるからってことですね。う~ん。素晴らしい…。
とりあえず1日1~2gのオメガ3脂肪酸を摂取すると痩せそう
問題は脂肪燃焼効果を得るには最低どれだけのオメガ3脂肪酸を摂取すれば良いのか分からないところなんですよねー。
まぁ、とりあえず1日1〜2gのオメガ3脂肪酸を摂ると差が出てくるみたいなんでこれが基準になりそうです。となれば、サバ缶水煮1個(190g)のオメガ3脂肪酸=約4.5gなんでサバ缶水煮を100g食べる、普通にサバやサーモンを100g食べるってのが良さそうですね。
オメガ3脂肪酸で海馬機能がアップする…!
2014年のローマ・サピエンツァ大学の動物実験によると、オメガ3脂肪酸を摂取すると頭が良くなるのか調べてみたそうです。
具体的には、生後19か月のオスの高齢マウスを以下の3つのグループに分けたそうです。
- オメガ3脂肪酸グループ:12匹のマウスに、オメガ3脂肪酸を含んだエサ(1kg当たり440mg)を与えた。
- オリーブオイルグループ:13匹のマウスに、オリーブオイルを含んだエサ(1kg当たり440mg)を与えた。
- コントロールグループ:12匹のマウスに、普通のエサを与えた。
因みに、エサは週5日、8週間与え続けたそうです。
気になる結果は、
- オメガ3脂肪酸の摂取によって、高齢マウスの海馬機能がアップした…!
- 具体的には物体の認識力・記憶力、空間記憶力、思い出す力がアップした…!
とのこと。
オメガ3脂肪酸を摂取することによって、老化による海馬機能の衰えを改善する可能性がある…!ってことですね。
因みにオメガ3脂肪酸グループのエサには、特に高濃度のエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)、ドコサペンタエン酸(DPA)が含まれていたそうです。
魚を食べまくると前立腺がんリスクが2,3倍も低くなる…!
2001年のカロリンスカ研究所の前向きコホート研究によると、魚と前立腺がんのリスクについて調べてみたそうです。
この研究はスウェーデン人の男性6,272人を対象に行ったそうで、追跡期間はなんと30年間だったそうな。
んで早速結果を見てみますと、
- 普段魚を全く食べない男性は、普段まぁまぁ~大量に魚を食べる男性に比べて、前立腺がんリスクが2,3倍も高かった…!
みたいです。
どうやら魚を食べまくると前立腺がんリスクを下げることが出来るみたいですねー。
魚・オメガ3脂肪酸で結腸がん・直腸がんのリスクが下がる…!
2008年のコロンビア大学の前向きコホート研究によると、魚(オメガ3脂肪酸)の摂取量と結腸がん・直腸がんリスクの関係を調べてみたそうです。
今回、実験に参加したのは22,071人でして、参加者には毎年全員、結腸がん直腸がんになっていないか報告してもらったそうな。また魚の摂取量については簡易版FFQ(食事摂取頻度調査票)を用いてチェックしたとのこと。
今回、実験に参加したのは22,071人でして、参加者には毎年全員、結腸がん直腸がんになっていないか報告してもらったそうな。また魚の摂取量については簡易版FFQ(食事摂取頻度調査票)を用いてチェックしたとのこと。
んで、気になる魚のアンケート部分なんですが、4種類の魚介類の平均摂取量について聞いてみたらしい。その4種類が以下となっておりました。
- マグロの缶詰
- 青魚(サバやサーモン、イワシ、ブルーフィッシュ、メカジキ)
- その他の魚
- エビやロブスター、ホタテ
アンケートでは上記4種類について、以下のカテゴリーで摂取頻度を答えてもらったそうです。
- 全く食べない・めったに食べない。
- 月1~3回食べる。
- 週1回食べる。
- 週2~4回食べる。
- 週5~6回食べる。
- 毎日食べる。
- 1日2回以上食べる。
これにより、1日の魚の摂取量とオメガ3脂肪酸の摂取量を計算したそうです。
1982年の研究開始から22年間の追跡調査をした結果がこちら。
- 期間中、500人の男性が結腸がん・直腸がんを発症していた。
- 魚を食べれば食べるほど、結腸がん・直腸がんリスクが低くなっていた(0.63)…!
- オメガ3脂肪酸についても上記と同じく、摂取量が多い程、結腸がん・直腸がんリスクが低くなっていた…!
- オメガ3脂肪酸を最も多く摂取していた人達は、結腸がん・直腸がんリスクが0.76も低くなっていた…!
どうやら、魚とそれに含まれるオメガ3脂肪酸が結腸がん・直腸がんのリスクを下げているみたいですねー。魚はやっぱり良いですな。
オメガ3脂肪酸はうつ症状に効果的…!しかもうつ病や双極性障害の患者さんにも効果アリ…!
2007年の長庚大学の研究によると、オメガ3脂肪酸はうつ病に効果的なのか調べてみたそうです。
まず研究者たちは、MEDLINEやEmbase、PsycINFOといったデータベースを用いて1966年~2006年8月までの範囲で該当する先行研究を検索してみたそうな。続いてその中から、実験期間が4週間以上であり、且つ、二重盲検・プラセボ対照のRCTをピックアップしていったとのこと。
要件を満たした研究は全部で10件だったそうで、総サンプル数は329人ということでした。これらのデータをメタ分析にかけてみたそうです。二重盲検・プラセボ対照・RCT・メタ分析って感じでなかなか質が高くてよろしいのではないでしょうか。
それでは結果を見てみましょう。
- オメガ3脂肪酸には、有意な抗うつ効果(効果量0.61)があった…!
- オメガ3脂肪酸には、うつ病の患者さんのうつ症状を有意に改善させる効果(効果量0.69)があった…!
- オメガ3脂肪酸には、双極性障害の患者さんのうつ症状を有意に改善させる効果(効果量0.69)があった…!
単純にうつ症状に効果的なだけでなく、うつ病や双極性障害といった気分障害の患者さんにも効果があったってのはすごいですね~。但し注意点もあって、個々の研究の質がかなり偏っていたみたいなんですよ。というのも出版バイアスがかなり激しかったんだとか。
出版バイアスとは、ネガティブな研究結果よりもポジティブな研究結果の方が発表されることが多いってバイアスのことを言いまして、例えば、何も効果がなかった…って結果(ネガティブな結果)よりも、これは効果アリ…!って結果(ポジティブな結果)の方が世に出回ることが多いってことです。まぁ、分かりますわな。
魚を1日83.3~112g食べると精神障害リスクが30%も減る…!
2007年のラス・パルマス・デ・グラン・カナリア大学の前向きコホート研究によると、オメガ3脂肪酸の摂取・魚の摂取と精神障害の関係について調べてみたそうです。この研究は、SUNコホート研究っていうものを使っておりまして、スペインの大学卒業生を対象に、高血圧や糖尿病、肥満、冠状動脈性心疾患(CHD)といった健康リスクと食事の関係を調べているものとなっております。
サンプル数は7,903人でして、食事アンケートからオメガ3脂肪酸の摂取量と魚の摂取量をチェックしつつ、追跡期間の2年間のうちに精神障害・うつ病・不安障害を発症していたかを見てみたそうな。
最後にデータを統計処理した結果、2年間のうちにうつ病が173件、不安障害が335件、ストレスによる障害が4件あったそうです。
んで気になる関係性ですが、オメガ3脂肪酸・魚をほとんど食べない人の精神障害リスクを1.00とすると、
- ちょっと食べる:0.72
- まぁまぁ食べる:0.79
- よく食べる:0.65
- すごく食べる:1.04
って感じだったそうな。
全体的にやはり定期的なオメガ3脂肪酸・魚の摂取はメンタルに良い影響を及ぼすみたいですねー。
では実際どれぐらい食べれば良いのかのベストについてですが、研究者曰く、
- 魚を1日83.3~112g食べると、精神障害リスクが30%も減るぞ…!
とのこと。
ちっこいサバ缶1個ぐらいっすね。これならそんなに難しくなくてよろしいですな。
魚・オメガ3脂肪酸のメンタル安定効果は特に女性に効きそう…!
2009年のノースウェスタン大学の研究によると、オメガ3脂肪酸・魚の摂取量とうつ症状が関係あるのか調べてみたそうです。
そもそもエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)といったオメガ3脂肪酸は、中枢神経の発達に重要で、魚で頭が良くなるとか脳に良いとか言われるのもここからきております。
んで、そんな脳に良いオメガ3脂肪酸がうつ病と関係あるんじゃないか…?って研究も出てきておりまして、例えば、大うつ病や産後うつの発症率は魚の摂取量の少なさが関係あるかもと言われているんですよね。しかし、一方で関係ないって研究結果も出ており、まだまだよく分からない感じです。
そんな中、2006年にブリストル大学からRCTのメタ分析・系統的レビューが出ました。この研究では、抑うつ症状にオメガ3脂肪酸が効くのかを調べた12件のRCTをメタ分析したんですが、結果は出版バイアスが高く、研究ごとの質がかな~りバラバラでよく分からなかったんですよ。
なんで今回研究者たちは、大規模コホート研究で確かめてみたんだとか。
具体的には、CARDIAっていう研究のデータセットを使ったみたいで、これがどういったものかといいますと、
- 1985~1986年時点で18~30歳だった5,115人のアフリカ系アメリカ人と白人の男女を対象に、ライフスタイルと心血管疾患(CVD)の危険因子を前向きコホート研究で調べたというもの
- 参加者はアラバマ州バーミンガム、イリノイ州シカゴ、ミネソタ州ミネアポリス、カリフォルニア州オークランドから募集
- 追跡調査は2年目(1987~1988年)、5年目(1990~1991年)、7年目(1992~1993年)、10年目(1995~1996年)、15年目(2000~2001年)、20年目(2005~2006年)の全6回
って感じ。
このデータセットの参加者5,115人から、7年目と10年目の調査に不参加だった人やデータが抜けている人、カロリー摂取量が極端な人、双極性障害の治療を受けていると自己申告した人を除外していったそうです。
因みに双極性障害の参加者をなぜ除外したかといいますと、1999年のブリガム・アンド・ウィメンズ病院の二重盲検・プラセボ対照のRCTで、オメガ3脂肪酸が双極性障害に有効だったから。というのも寛解期間(症状安定期間)が有意に長かったんですよね。そのためうつ症状の効果を確かめる今回の研究から除外したわけです。
話しを戻しまして、除外した結果、最終的なサンプル数は3,317人になったそうな。
続いて魚の摂取量とエイコサペンタエン酸(EPA)・ドコサヘキサエン酸(DHA)の摂取量についてですが、これは食事アンケートから摂取量をチェックしたとのこと。
うつ病の症状については以前に登場したCES-Dスケールっていううつ病自己評価尺度(60点満点・全20項目)を用いてチェックしたらしい。このスケールで16点以上だった人又は自己申告で抗うつ薬を使用していると答えた人をうつ症状ありとしたみたい。
因みに食事とうつ症状をチェックした時期は、
- 食事:7年目(1992~1993年)
- うつ症状:10年目(1995~1996年)、15年目(2000~2001年)、20年目(2005~2006年)
となっておりました。
最後にデータを統計処理した結果、以下のことが分かったそうです。
- 3,317人の平均年齢は、10年目の時点で32.1歳、年齢幅は24~42歳だった。
- 参加者の22.4%(744人)が10年目の時点でCES-Dスケールが16点以上だったり、抗うつ薬を使っていた…!
- 男性よりも女性の方がCES-Dスケールの平均スコアが高かった。また平均BMIが高い、身体活動レベルが低い、別居や離婚している可能性が高い、失業している場合が高い、年収が低い、魚の摂取量の中央値が低いという傾向も見られた…!
- 全体的にはエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)については小さいが逆相関があった。EPA+DHAについては有意な逆相関があった…!
- 性別を分けて分析した結果、女性のみエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)、EPA+DHAで有意で大きな逆相関があった…!
- 男性は有意な関係性は見当たらなかった…!
これらをみると、魚・オメガ3脂肪酸の摂取量と慢性的なうつ症状リスクは逆相関の関係みたいですね。但し、女性だけが関係あって男性は関係ないと。
オメガ3脂肪酸は双極性障害のうつ症状に効果あり…!躁状態には無意味っぽい…!
まず研究者たちは、PubMedやCINAHL、Web of Science、コクランライブラリといったデータベースを用いて、2010年9月1日までに発表された双極性障害とオメガ3脂肪酸の関係を調べた先行研究を検索してみたそうな。
続いて、サンプル数が10人より多いか、実験期間が4週間以上か、RCTかなどをチェックし、質の高い研究をピックアップしていったらしい。
最終的に基準を満たした研究は、5件でして総サンプル数は291人になったみたい。メタ分析としては小規模ですが、まぁ、仕方ないでしょう。
最後にメタ分析にかけてみた結果、以下のことが分かったそうです。
- 双極性障害のうつ状態に対するオメガ3脂肪酸の効果量は0.34で中程度の有意な効果があった…!
- 双極性障害の躁状態に対するオメガ3脂肪酸の効果量は0.20で有意な効果がなかった…。
つまり、双極性障害のうつ症状にはオメガ3脂肪酸がサブ的に使えそうだけど、躁状態には無意味だと。これを見ると、うつ病にオメガ3脂肪酸が効果的だったのも頷けますね~。
オメガ3脂肪酸はうつ病に小~中程度の効果あり…!EPAは効果があってDHAは効果がないっぽい…!摂取量は1日1g以下のEPAがポイント…!
2019年の深圳市南山区慢性疾患管理センターの研究によると、うつ病にオメガ3脂肪酸が有効なのか、EPA・DHAは有効なのか、ベストな量はどのぐらいかについてメタ分析で調べてみたそうです。
そもそも先行研究により、オメガ3脂肪酸・エイコサペンタエン酸(EPA)・ドコサヘキサエン酸(DHA)がうつ病の症状改善に効果があることが分かってきておりました。そして効果を調べたメタ分析もいくつかございまして、それらによると、EPAの方がDHAよりも効果が高い可能性があったんですよね。
例えば、
- 2014年のカターニア大学のメタ分析:EPAを50%より多くした
- 2011年のニューヨーク州精神医学研究所のメタ分析:EPAを60%より多くした
- 2016年のゴールウェイ大学のメタ分析:EPAを80%より多くした
場合は、DHAを50%より多くした場合、60%より多くした場合、80%より多くした場合よりも明らかに効果が高かったそうな。そしてEPAとDHAのベストな割合は2:1か3:1ぐらいって感じだったっぽい。
しかし、これらはまだよく分かっていなかったんで、今回メタ分析でチェックしてみることにしたんだとか。
ということでまず研究者たちは、2017年12月20日までに発表されている該当研究を、PubMedとEmbaseで検索してみたそうです。その結果、179件のRCTがあったそうな。また系統的レビューやメタ分析の参考文献もチェックしたそうで、そちらからは25件の該当研究が見つかったらしい。
次にその中から質の高い研究をピックアップしていったそうで、最終的に基準を満たしていた研究は26件だったとのこと。この26件の総サンプル数は2,160人(オメガ3脂肪酸グループ1,089人、プラセボグループ1,071人)ということで、これらのデータをメタ分析にかけてみたそうな。
気になる結果は、
- オメガ3脂肪酸は、うつ病の症状改善に小~中程度の効果があった…!
- ドコサヘキサエン酸(DHA)は、うつ病の症状改善に有意な効果を示せなかった…。
- エイコサペンタエン酸(EPA)は、うつ病の症状改善に有意な効果を示した…!
とのこと。
やはり先行研究同様、オメガ3脂肪酸はうつ症状に効きそうですし、特にEPAが良い感じみたいですな。
では、気になるベストな摂取量についてですが、
- 1日1g以下のEPAを摂取すると、うつ病の症状改善に効果的だった…!
- 1日1.5gと1日2gのEPAを摂取してみたが、有意な結果は見られなかった…。
ってことなんで、1日1gまでの摂取が良いっぽいですね~。
RCTの系統的レビュー・メタ分析で調べてみた結果、EPA+DHAのうち60%以上がEPAであるもので1日1g~2gEPAを摂取するとうつ病の症状改善に効果を発揮するみたい…!
2023年のローハンプトン大学の研究によると、オメガ3脂肪酸・EPA・DHAが成人の不安障害やうつ病の症状改善に役立つのか、RCTの系統的レビューとメタ分析で調べてみたそうです。
そもそも2020年の世界の疾病負荷研究(GBD:世界の疾病負担研究)では、204の国と地域を対象に病気について調べているんですが、2019年に最も引き起こした精神障害が不安障害とうつ病だったそうなんですよね。また、WHOによれば、世界中で3億人以上の人々が不安症に悩み、また2億8,000万人の人々がうつ病に悩まされているらしい。
更に最近ようやく落ち着いてきましたが、2021年の研究によれば、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる2020年の204の国と地域における不安障害とうつ病は増加傾向であったそうです。具体的には、不安障害の発症者は25.6%増加、大うつ病の発症者も27.6%増加していたんだとか。
こう見ると、世界的に年々精神障害、特に不安障害とうつ病が増えてきており、コロナが更にそれを加速させたって感じですね。
特にエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)は、神経膜の調節や神経伝達と受容体の発現、抗酸化・抗炎症作用、神経細胞の成長など不安やうつに対してかなり効果がありそうな感じなんですな。
また先行研究により、不安や抑うつ状態の人は総じてオメガ3脂肪酸(EPAやDHAなど)が少ない傾向にあるというのも分かっております。んが、しかし、先行するこれらを調べたメタ分析の結果はかなりバラバラで効果あり…!って結果の研究もあれば、全く効果なんてなかったぞ…!って報告する人もいたりするんですよ。他にもEPAは効果があるけどDHAは効果がないなんて話もある訳でして…。
…っと、そんな感じで、よう分からん部分があるんで、今回これらをはっきりさせるべく、RCTの系統的レビューとメタ分析を行ってみることにしたんだとか。
まず研究者たちは、PubMed(MEDLINE)やCINAHL、PsycINFO、Cochrane Library、Web of Scienceといったデータベースを活用し、2022年7月25日までに発表された査読済みの該当研究を検索してみたそうです。
またその際に、不安障害やうつ病のある18歳以上の成人を対象としているかをチェックしつつ、他の病気を持っている人なんかを除外していったらしい。すると791件の研究がヒットしたそうな。
続いて重複しているものや質の低い研究なんかがないか精査していったそうで、最終的に基準を満たした研究は10件だったらしい。この10件の総サンプル数は1,509名でして平均年齢は46.9歳、女性の割合は68%、実験の平均期間は11週間とのことでした。
これらのデータを用いてメタ分析にかけてみたそうです。
では結果を見てみましょう…!
- 10件のRCTを用いてオメガ3脂肪酸の参加者833名とプラセボ656名の効果を見てみた。因みに平均実験期間は11週間。
- オメガ3脂肪酸の効果は統計的に有意であり効果サイズは小(SMD=-0.36)だった…!
- 但し、それぞれの研究結果のバラバラさが高く、特に効果量が大きかった研究があったので除いてみると、有意さがなくなった(SMD=-0.12)
- EPA+DHAのうち60%未満のEPAを含んだうつ病研究では、EPA+DHAのうち18.6%のEPAを含んでおり、109名の参加者が使用、プラセボは111名だった。因みに平均実験期間は8週間。
- 結果は統計的な有意差はなかったものの効果の推定値は得られた(SMD=0.05)
- EPA+DHAのうち60%以上のEPAを含んだうつ病研究では、EPA+DHAのうち86.9%のEPAを含んでおり、502名の参加者が使用、プラセボは429名だった。因みに平均実験期間は10.7週間。
- 結果は統計的に有意であり効果サイズは小(SMD=-0.16)だった…!
- またEPA+DHAのうち77.6%のEPAを含んでおり、222名の参加者が使用、プラセボは227名だった。因みに平均実験期間は11.5週間。
- 結果は統計的に有意であったが(SMD=-1.11)、効果の幅が広く(-2.16、-0.07)、それぞれの研究結果のバラバラさも高かった。
- そのため特に効果量が大きかった研究を除外してみると、有意さがなくなった(SMD=-0.14)
- またEPA+DHAのうち84%のEPAを含んでおり、724名の参加者が使用、プラセボは702名だった。因みに平均実験期間は11週間。
- 結果、統計的に有意であったが(SMD=-0.39)、それぞれの研究結果がかなりバラバラだった。
- EPA+DHAのうち60%以上のEPAを含んだうつ病研究を用いて、ベストな摂取量を調べてみた。
- 5件のRCTを用いて、1日1.1gのEPAを摂取した399名の参加者とプラセボ395名を平均実験期間10.4週間で調べた結果、統計的に有意(SMD=-0.17)だった…!
- 4件のRCTを用いて、1日1.2gのEPAを摂取した222名の参加者とプラセボ227名を平均実験期間11.5週間で調べた結果、統計的に有意であったが(SMD=-1.11)、効果の幅が広く(-2.16、-0.07)、それぞれの研究結果のバラバラさも高かった。そのため特に効果量が大きかった研究を除外してみると、有意さがなくなった(SMD=-0.14)
- 9件のRCTを用いて、1日1.1gのEPAを摂取した621名の参加者とプラセボ624名を平均実験期間10.9週間で調べた結果、統計的に有意(SMD=-0.45)だった…!これは1日1.1gのEPAの摂取がプラセボよりも、うつ性自己評価尺度(SDS:Self-Rating Depression Scale)でのうつ病の重症度の平均を0.45有意に改善する効果があった…!
- 3件のRCTを用いて、1日2.1gのEPAを摂取した103名の参加者とプラセボ104名を平均実験期間13.3週間で調べた結果、有意ではない効果(SMD=-0.20)があった。
以上をまとめると、
- EPA+DHAのうち60%以上がEPAであるもので、1日1g~2gEPAを摂取するとうつ病の症状改善に効果を発揮する…!
ということになりましょう。
オメガ3脂肪酸は脳の発達や機能をアップさせ精神疾患リスクを下げる…!
2016年のコペンハーゲン大学などの研究によると、オメガ3脂肪酸が脳の発達や機能にどのような効果をもたらすのかレビューしてみたそうです。
なんでも2001年のサウスフロリダ大学の研究によれば、脳におけるDHAの蓄積は、子宮内及び新生児期から2歳までに起こるそうで、脳内の高レベルのDHAは生涯にわたって維持されるんだとか。胎児や赤ちゃんの時の脳のオメガ3脂肪酸レベルが一生続くってのは何ともすごい話ですな。
特に妊娠後期の脳におけるDHAレベルは、全体的な体内DHAレベルよりも大幅に高いんだとか。んで、2歳までのDHAの主な摂取方法は、母親のお腹の中にいる時は母親からの供給、乳幼児期は母乳や離乳食などの食事とのこと。その後、脳のDHAの蓄積は小児期まで続くそうで、低下はしてくるものの、少なくとも就学までの年齢まではDHAレベルは依然として高いままらしい。
このような経緯から、乳幼児期に脳内で高レベルのDHAが達成されると、その後の人生を通じて維持され、それらは最適な食事からの供給にも依存しているみたい。但し、DHAが乳児の視覚発達に関係あることは分かっているものの、認知の発達との関係はまだはっきりとは分かっていないそうです。
そして更によく分からないのが成人がオメガ3脂肪酸を積極的に摂取すると脳機能にどのような影響をもたらすのかです。
いくつかの研究では、DHAは成人後期の認知機能や行動に重要な影響を与えると出ているそうな。
また、習慣的にDHAを摂取している健康な成人の若者はそうでない若者に比べて、記憶力がアップしたという研究もあるとのこと。
更にDHAは精神疾患にも効果があるという研究がありまして、
- 統合失調症
- 大うつ病
- 双極性障害
の生涯発症リスクが低下するそうな。
つまり、DHAが認知機能の低下を改善し、それが精神疾患予防になるみたい。
ということで、オメガ3脂肪酸は子ども、大人、妊婦さんに限らず誰でも積極的に摂取していくと良さそうな感じです。
魚の摂取と慢性疾患リスクについてアンブレラレビューを行ってみた…!
2020年のセムナン医科大学の研究によると、魚の摂取と慢性疾患リスクについてアンブレラレビューを行ってみたそうです。
皆さんご存知の通り、魚にはオメガ3脂肪酸(EPA、DHA)が豊富に含まれておりまして、これにより心血管疾患や高血圧、体内炎症、酸化ストレスなど、様々な健康リスクを下げてくれると先行研究で出ております。
んがしかし、それらがどの程度信頼できるエビデンスなのか、あんまりチェックされていないのが実情でした。そこで今回アンブレラレビューを用いてガッツリ見てみることにしたんだとか。
まず研究者たちは、2019年10月までに発表された該当する前向きコホート研究のメタ分析をPubMedとScopusで検索してみたそうな。すると3,265件の研究がヒットしたとのこと。次にこの中で重複している物や質の低い研究を除いていったそうで、最終的に残ったメタ分析は34件だったみたい。
それでは結果を見ていきましょう。
まずは魚の摂取と心血管代謝疾患や死亡リスクについてです。
- 心筋梗塞:1日100g食べると25%(RR0.75)減る(エビデンスレベル:普通)
- 心血管疾患による死亡リスク:1日100g食べると25%(RR0.75)減る(エビデンスレベル:普通)
- 心不全:1日100g食べると20%(RR0.80)減る(エビデンスレベル:普通)
- 脳卒中:1日100g食べると14%(RR0.86)減る(エビデンスレベル:普通)
- 冠状動脈性心疾患:1日100g食べると12%(RR0.88)減る(エビデンスレベル:普通)
- 全死亡率:1日100g食べると8%(RR0.92)減る(エビデンスレベル:普通)
- 心不全(魚のフライを食べた場合):食べる頻度が高いと40%(RR1.40)増える(エビデンスレベル:低い)
- 冠状動脈性心疾患による死亡率:1日100g食べると35%(RR0.65)減る(エビデンスレベル:低い)
- 2型糖尿病(オメガ3脂肪酸が多い魚を食べた場合):食べる頻度が高いと11%(RR0.89)減る(エビデンスレベル:低い)
- 冠状動脈性心疾患(オメガ3脂肪酸が多い魚を食べた場合):食べる頻度が高いと15%(RR0.85)減る(エビデンスレベル:低い)
- 高血圧:1日100g食べると5%(RR1.05)増える(エビデンスレベル:低い)
- 心房細動(不整脈):1日100g食べると40%(RR0.60)減る(エビデンスレベル:低い)
- 2型糖尿病:1日100g食べると9%(RR1.09)増える(エビデンスレベル:低い)
- メタボ:1日100g食べると40%(RR0.60)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 心不全(魚のフライ以外を食べた場合):食べる頻度が高いと31%(RR0.69)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 2型糖尿病(赤身魚を食べた場合):食べる頻度が高いと4%(RR0.96)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 冠状動脈性心疾患(赤身魚を食べた場合):食べる頻度が高いと2%(RR0.98)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
次は魚の摂取とがんリスクについてです。
- 肝臓がん:1日100g食べると35%(RR0.65)減る(エビデンスレベル:普通)
- 骨髄性白血病:食べる頻度が高いと40%(RR1.60)増える(エビデンスレベル:低い)
- 胃がん:1日100g食べると16%(RR1.16)増える(エビデンスレベル:低い)
- 前立腺がんによる死亡率:食べる頻度が高いと63%(RR0.37)減る(エビデンスレベル:低い)
- 膀胱がん:食べる頻度が高いと14%(RR0.86)減る(エビデンスレベル:低い)
- 大腸がん:1日100g食べると7%(RR0.93)減る(エビデンスレベル:低い)
- 全てのがん死亡率:1日100g食べると2%(RR0.98)減る(エビデンスレベル:低い)
- 乳がん:1日100g食べると0%(RR1.00)と変わらない(エビデンスレベル:低い)
- 前立腺がん:食べる頻度が高いと2%(RR1.02)増える(エビデンスレベル:低い)
- 卵巣がん:食べる頻度が高いと4%(RR1.04)増える(エビデンスレベル:低い)
- 膵臓がん:1日100g食べると6%(RR1.06)増える(エビデンスレベル:低い)
- 食道がん:食べる頻度が高いと13%(RR0.87)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 多発性骨髄腫:食べる頻度が高いと6%(RR0.94)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 肺がん:食べる頻度が高いと5%(RR0.95)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 慢性リンパ性白血病:食べる頻度が高いと1%(RR0.99)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 子宮内膜がん(子宮体がん):1日100g食べると0%(RR1.00)と変わらない(エビデンスレベル:非常に低い)
- 白血病:食べる頻度が高いと2%(RR1.02)増える(エビデンスレベル:非常に低い)
- 口腔がん:食べる頻度が高いと3%(RR1.03)増える(エビデンスレベル:非常に低い)
- 腎臓がん:食べる頻度が高いと7%(RR1.07)増える(エビデンスレベル:非常に低い)
- 非ホジキンリンパ腫:食べる頻度が高いと8%(RR1.08)増える(エビデンスレベル:非常に低い)
最後は魚の摂取とその他についてです。
- うつ病:食べる頻度が高いと12%(RR0.88)減る(エビデンスレベル:普通)
- アルツハイマー病:1日100g食べると59%(RR0.41)減る(エビデンスレベル:低い)
- 加齢黄斑変性(全体):1日100g食べると56%(RR0.44)減る(エビデンスレベル:低い)
- 関節リウマチ:1日100g食べると25%(RR0.75)減る(エビデンスレベル:低い)
- ウエスト周りの肥満:1日100g食べると17%(RR0.83)減る(エビデンスレベル:低い)
- 股関節の骨折:食べる頻度が高いと8%(RR0.92)減る(エビデンスレベル:低い)
- 加齢黄斑変性(後期):食べる頻度が高いと24%(RR0.76)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 加齢黄斑変性(前期):食べる頻度が高いと22%(RR0.78)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 認知症:1日100g食べると35%(RR0.65)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 喘息:食べる頻度が高いと10%(RR0.90)減る(エビデンスレベル:非常に低い)
- 炎症性腸疾患:食べる頻度が高いと12%(RR1.12)増える(エビデンスレベル:非常に低い)
いずれも太字黄色の物は信頼して良い感じですね。その他の物は可能性アリって感じや関係ないものとなっております。
以上の結果をまとめると、
- 魚の摂取は、全死亡率、心血管疾患による死亡リスク、冠状動脈性心疾患リスク、心筋梗塞リスク、脳卒中リスク、心不全リスク、うつ病リスク、肝臓がんリスクの低下に役立つ…!
って感じ。
オメガ3脂肪酸は大事…!ではどれぐらい魚を食べれば良いのか…?
オメガ3脂肪酸や魚のおすすめ摂取量を知るに当たり参考になるのが2016年のワシントン州立大学の研究になります。これは2015年版のアメリカ食事ガイドラインでして、中身を見てみると、
- 様々な魚介類を1週間に約240g(1週間に2食)食べることをオススメするよ…!
と記載があるんですな。
これを参考にするとEPAとDHAの平均摂取量は1日250mgって感じ。
また2011年のワシントン州立大学の研究(2010年版のアメリカ食事ガイドライン)によると、鮭やニシン、サバ、マグロなどの脂肪の多い魚はビタミンDが豊富らしく、赤身魚よりもEPAとDHAの含有量が多いみたい。
- 脂肪の多い魚(鮭、イワシ、ニシン、サバ、マグロなどの油の多い冷水魚)を1週間に1回(120g)食べるとオメガ3脂肪酸の推奨摂取量(1日250mg)を達成できる…!
- エビ、ロブスター、ホタテ、タラは複数回食べないと推奨摂取量を達成できない…!
とのこと。
青魚だと少ない量で推奨摂取量を満たせるけど、赤身魚は多めに食べないといけないかもですね。
抗炎症作用の高いオススメ食品は魚(特に青魚)…!
2012年のアムステルダム自由大学の研究によると、オメガ3脂肪酸とCRP(C反応性タンパク)の関係について調べてみたそうです。
この研究は、フィンランド在住の42~60歳の健康な男性1,395人を対象にしたもので、全員の血中のオメガ3脂肪酸とCRPをチェックしたと言うもの。併せて髪の毛に含まれる水銀も見てみたんだとか。因みになぜ水銀をチェックしたかと言いますと、魚に含まれる環境汚染物質の代表的な物が水銀なんですよね。なんでもしかしたら炎症とも関係がある可能性があったんですな。
最後に集まったデータを統計処理した結果、
- オメガ3脂肪酸とCRPは有意な逆相関の関係にあった…!
とのこと。
やっぱりオメガ3脂肪酸に含まれる抗炎症作用はすばらしいですね。
また詳しく見てみると、
- DHA(ドコサヘキサエン酸)は有意な逆相関の関係にあった…!
- EPA(エイコサペンタエン酸)は関係なかった
- ALA(α-リノレン酸)は関係なかった
って感じで、どうやらポイントはDHAみたい。
因みに水銀とCRPは関係がなかったそうです。
ということで、お魚(特に青魚)を積極的に食べて抗炎症作用を受けると良さげです。
魚・オメガ3脂肪酸とガンリスクについて観察研究のメタ分析のアンブレラレビューを行ってみた…!
2020年の延世大学校などの研究によると、魚・オメガ3脂肪酸とガンリスクについて観察研究のメタ分析のアンブレラレビューを行ってみたそうです。
魚・オメガ3脂肪酸には抗炎症作用がありまして、それによりがんリスクが低下する可能性があったりします。しかし、矛盾する結果も出ていて良く分かっていない部分もあったんだとか。そこで今回、初のアンブレラレビューを行ってみることにしたらしい。
まず研究者たちは、2018年12月1日までに発表された該当する系統的レビューとメタ分析をPubMed、Embase、コクランで検索してみたそうな。その後、検索にヒットした研究の中で重複している研究を除いていったみたい。
すると合計598件の研究が見つかったんだとか。次にこの中の研究の質をチェック、良い感じの物をピックアップしていったそうです。
最終的に基準を満たした研究は15件でして、これらを基に、魚・オメガ3脂肪酸とガンリスクの関係を見てみたとのこと。
結果、
- 説得力のあるエビデンス→なし…。
- 非常に可能性のあるエビデンス→なし…。
- 可能性のあるエビデンス→なし…。
- 低いエビデンス→あり…!
って感じ。
低いエビデンスレベルのものしかなかったのは残念ですね~。
では、それらが何か見てみましょう。
- オメガ3脂肪酸の摂取で肝臓がんリスクが統計的に有意に低下していた…!
- オメガ3脂肪酸の摂取で乳がんリスクが統計的に有意に低下していた…!
- オメガ3脂肪酸の摂取で前立腺がんリスクが統計的に有意に低下していた…!
- オメガ3脂肪酸の摂取で脳腫瘍リスクが統計的に有意に低下していた…!
いくつかのがんリスク低下に魚やオメガ3脂肪酸が良いかも…?って感じですね。
それと、オメガ3脂肪酸の摂取で子宮内膜がん(子宮体がん)リスクと皮膚がんリスクが統計的に有意に低下していたんですが、個別の研究は1件のみでエビデンスレベルは評価できなかったとのこと。
ということでオメガ3脂肪酸の研究はたくさんあるけど、がんリスクについては質の低い研究ばっかで良く分からない感じ。今後の研究に期待って感じですね。
オメガ3脂肪酸と生理痛の関係について調べてみた…!
1995年のオーフス大学の研究によると、オメガ3脂肪酸の摂取量と生理痛の関係について調べてみたそうです。
この研究は、現在妊娠しておらず経口避妊薬を使用していない健康なデンマーク人の女性181人が参加したもので年齢は20~45歳の方々だったそうな。
研究の流れは、アンケートに答えてもらったと言うもので、月経歴や現在の症状、全般的な健康状態、社会経済的状況、いつもの食生活に聞いてみたらしい。更に4日間の食事記録も提出してもらい、1日の栄養素を出してみたんだとか。
最後にデータをまとめてみた結果、
- 社会経済的状況や人体計測データと生理痛は関係がなかった…。
- んがしかし、動物性食品や魚介類の摂取量が少ないこと、特定の栄養素の摂取量が少ないことと生理痛は関係があった…!
- 生理痛のある女性の食事中のオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸の比率が平均0.24だった…!
とのこと。
更に詳しく見てみると、
- オメガ3脂肪酸の摂取量が少ないことによるビタミンB12不足
- オメガ3脂肪酸の摂取量が少ないことによるオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸の比率の低さ
- オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸の比率の低さによるビタミンB12不足
のいずれにおいても、有意に高かったとのこと。
つまり、生理痛はオメガ3脂肪酸不足が原因…!オメガ3脂肪酸の摂取量が多いほど生理痛が軽くなる…!って感じだったみたい。
オメガ3脂肪酸と月経困難症の関係について系統的レビューとメタ分析を行ってみた…!
2023年のディーキン大学の研究によると、オメガ3脂肪酸と月経困難症の関係について系統的レビューとメタ分析を行ってみたそうです。
月経困難症ってのは、月経出血中の下腹部や背中の痛みを伴うけいれんが特徴の最も一般的な婦人科疾患でありまして、世界中で月経のある女性の45%~95%が罹患していると言われております。一般的な症状としては、下腹部の痛み、骨盤の痛み、背中の痛み、大腿部の痛みなんかでして、他にも頭痛や吐き気、嘔吐、下痢などの全身症状もあるとのこと。つまり生理痛と呼ばれているものですな。
そして困っちゃうのが生理痛(月経困難症)の激しい痛みや症状は、気分や睡眠の質、勉強や仕事の生産性を低下させていしまい、その結果、学校や仕事の欠席も増やし、全体的な生活の質を下げちゃうってことです。その為、女性にとってこの効果的な治療法は非常に重要とのこと。
そんな生理痛(月経困難症)の研究は結構進んでいるようでいない感じみたいでして、ざっくりポイントをまとめると、
- 生理痛(月経困難症)の原因は、過剰なプロスタグランジンの生成が関係している可能性が高く、これが月経中の炎症プロセスに関係しているみたい
- 実際、
- プロスタグランジンの合成を減らすことで生理痛(月経困難症)の効果的に治療が出来ている
- 主な治療法として、非ステロイド性抗炎症薬とアセトアミノフェン(パラセタモール)が有効である
- ホルモン避妊薬やその他の鎮痛剤、体を温める、休む、運動、なども痛みの緩和に役立つ
- 非ステロイド性抗炎症薬は、生理痛(月経困難症)症状を最大70%も緩和するという研究結果もある。一方で消化不良や頭痛、眠気などの副作用が見られるパターンや、使用が禁忌に該当するパターンもある
って感じです。
そんな中、特に禁忌に該当する女性にとって非常に期待されているのがオメガ3脂肪酸なんですな。上記の研究の通り前々からオメガ3脂肪酸は生理痛の痛みを軽減するかも…!となっていたんですよ。また普段から薬はちょっと使いたくない…って方も期待しておりました。
但し、実際の効果がはっきり分かっていなかったんで、この度、系統的レビューとメタ分析(質の高い研究)を用いて調べてみることにしたんだとか。
まず研究者たちは、2023年1月1日までに発表された該当研究を、Embase、Scopus、Web of Science、EBSCOhost(MEDLINE、CINAHL、AMEDを含む)で検索してみたそうな。すると合計179件の研究が見つかったとのこと。次にこの中で重複している研究や質の低い研究を除いていったらしい。
最終的に選ばれた研究は12件でして、これらを用いて系統的レビューを、このうちの8件を用いてメタ分析を行ってみたそうです。
因みに12件の研究の特徴は以下な感じでした。
- 研究パターン:12件中1件がRCTのクロスオーバーデザイン、11件がRCTだった
- 総サンプル数:881名
- 平均年齢:21.7歳、範囲13~33歳
- 最も一般的なオメガ3脂肪酸の摂取量:1000mg
- 摂取期間:2~3か月
では結果を見てみましょう。
- 系統的レビューの結果、オメガ3脂肪酸は月経困難症(生理痛)の痛みの軽減に効果があった…!
- 月経困難症(生理痛)の痛みの重症度が22%~66%有意に軽減していた…!
- メタ分析の結果、オメガ3脂肪酸は月経困難症(生理痛)の痛みの軽減に大きな効果(d=-1.020)があることを示していた…!
- 鎮痛剤を使用した7件の研究のうち6でオメガ3脂肪酸を使うと、鎮痛剤の使用が有意に減少していた…!
つまり、オメガ3脂肪酸は生理痛の痛み対策にかなり効果があるぞ…!しかも薬の使用も減るぞ…!って感じ。素晴らしいですね~。まぁ、研究の質や研究数はまだまだなところもあるみたいですがとりあえず魚は積極的に食べておきたいところですね~。
因みにこの研究でのオススメは、
- オメガ3脂肪酸を1日300~1800mg摂取する、これを2~3ヶ月間続けると良い…!
となっておりました。
これで月経困難症(生理痛)の女性の痛みと鎮痛剤の使用を減らすことができる可能性があるとのこと。
因みにサバ缶水煮1個(190g)のオメガ3脂肪酸含有量が大体4500mgなんで、1/3も食べれば十分ってことですね。これはハードルが低くてよろしいですな。
ってことで毎日ちょっとずつ青魚を食べていくと2~3ヶ月後に効果が出る可能性アリ。困っている方は参考にしてみてもよろしいのではないでしょうか。
個人的考察
因みにオススメは毎度おなじみサバ缶です。手軽で保存も効きますんでよろしいかと。これを知って150種類以上のサバ缶を食べてどれがコスパ的にいいのか調べたデータもあるんで、どのサバ缶がおいしいの…?コスパが良いの…?ってことを知りたい方は下記からご覧ください。
参考文献
リンク